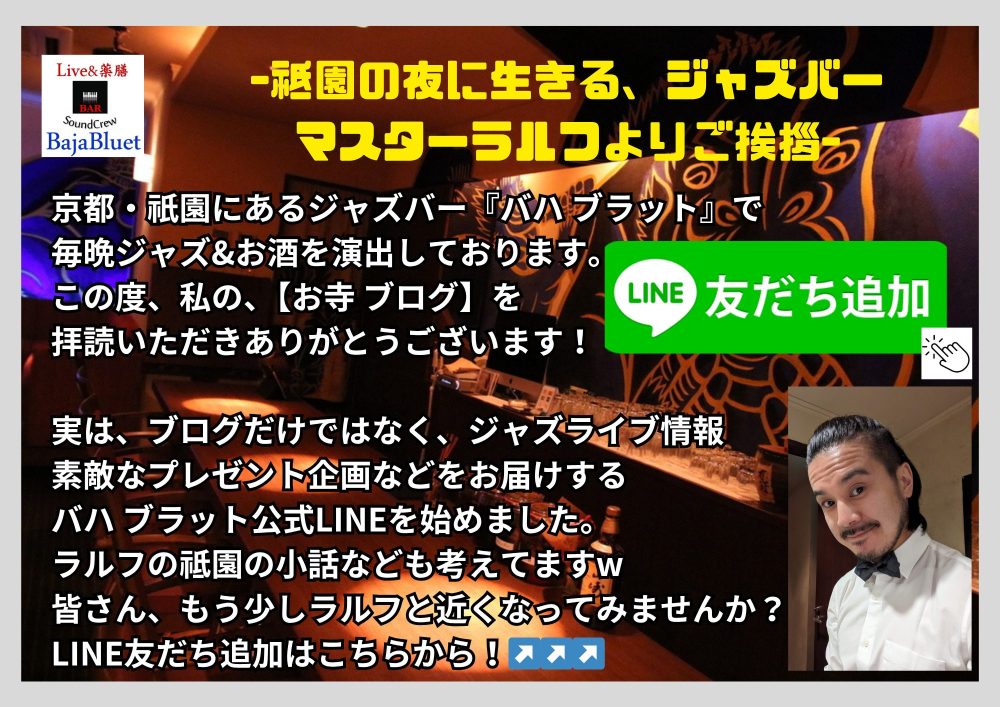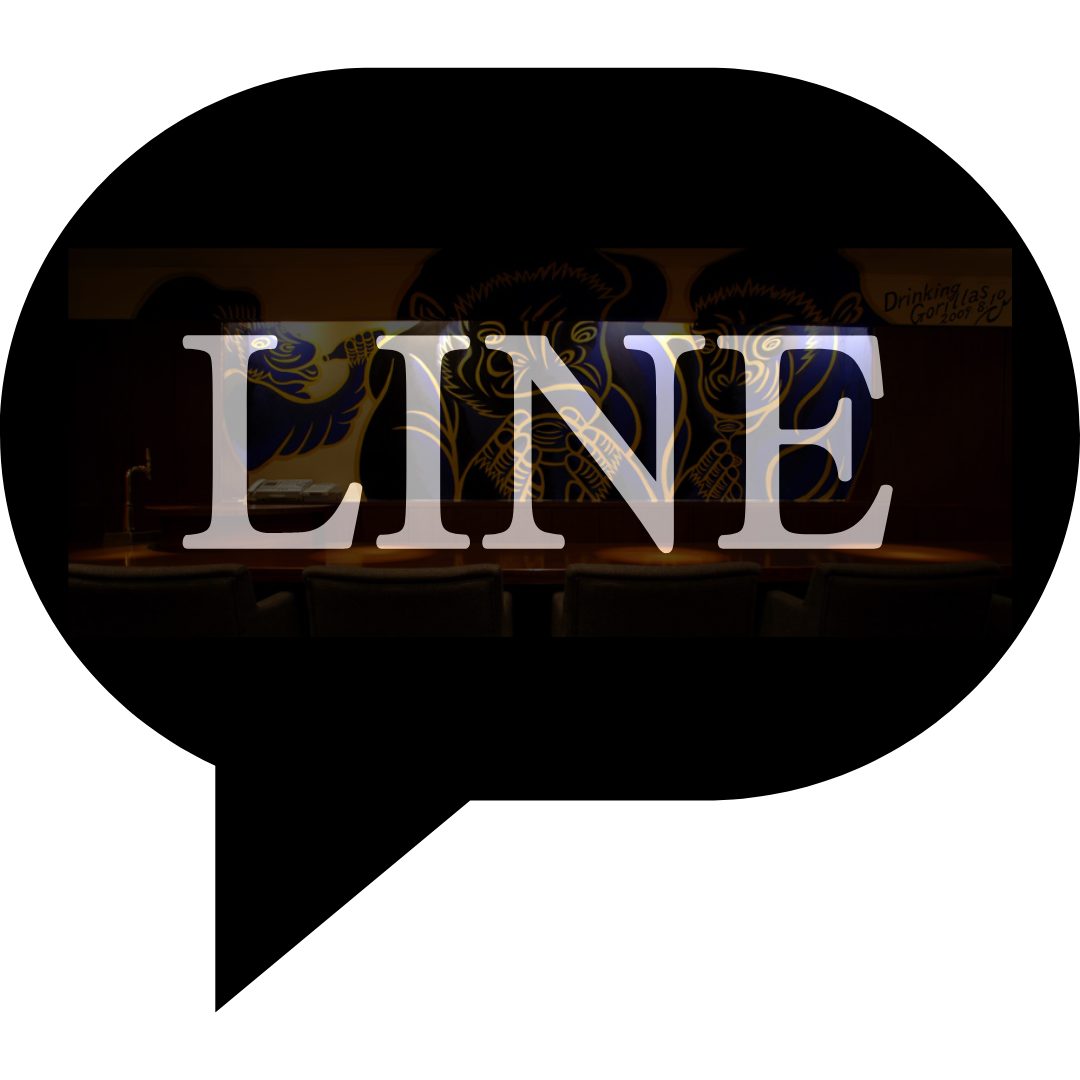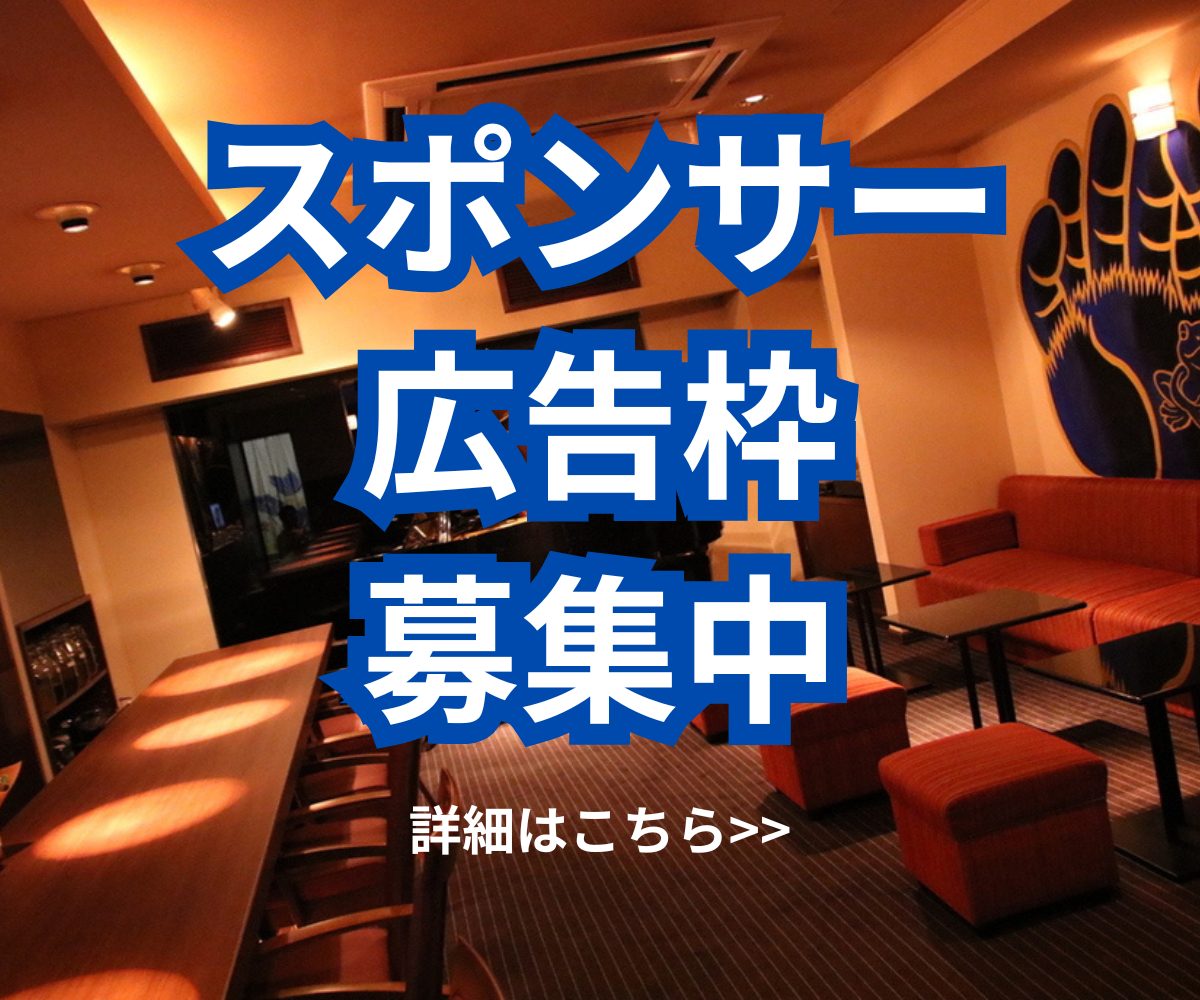京都 ラルフ ブログを拝読いただきありがとうございます。
京都の清水寺で御朱印巡りを楽しみませんか?清水寺は音羽山の中腹に建つ北法相宗の大本山で、国宝の本堂や有名な「清水の舞台」があり、年間500万人もの観光客が訪れる人気スポットです。
目次
清水寺の御朱印とは
清水寺の御朱印は、参拝の証として人気が高く、全11種類もの豊富な種類が用意されています。通常の御朱印の初穂料(値段)は300円で、境内の3か所で受け付けています。
御朱印をいただける場所と時間
清水寺では本堂横、阿弥陀堂、音羽の滝の3ヶ所の納経所で御朱印をいただけます。どの納経所も拝観ルート上にあるため、効率よく参拝と御朱印集めができるようになっています。
受付時間は朝8時から夕方18時(季節により18時30分)までとなっており、混雑する観光シーズンでも4人体制で手書き(直書き)に対応しているため、比較的スムーズに授与されます。
御朱印の種類と特徴
清水寺は西国三十三所や洛陽三十三所観音霊場など複数の霊場の札所となっており、それぞれの御朱印があります。
本堂横の納経所で授与される御朱印
本堂の御朱印(西国三十三所):中央に「大悲閣」の文字が入る代表的な御朱印
御詠歌の御朱印(西国三十三所)
善光寺堂の御朱印(洛陽10番)
奥の院の御朱印(洛陽11番)
本堂の御朱印(洛陽12番)
朝倉堂の御朱印(洛陽13番)
泰産寺の御朱印(洛陽14番)
その他(神仏霊場巡拝の道)
阿弥陀堂の納経所で授与される御朱印
阿弥陀如来の御朱印(法然上人二十五霊場)
御詠歌の御朱印(法然上人二十五霊場)
阿弥陀如来の御朱印(洛陽六阿弥陀)
音羽の滝の納経所で授与される御朱印
不動明王の御朱印
また、期間限定の御朱印として「月参り巡礼の御朱印」や「成就院の御朱印」なども特別に授与されることがあります。
おすすめの御朱印と御朱印帳
清水寺では、お寺の名前の由来となった音羽の滝の「不動明王」の御朱印や、阿弥陀堂の「阿弥陀如来」「法然」の御朱印もとてもおすすめです。
また、オリジナルの御朱印帳も販売されており、仏足石(お釈迦様の足跡を刻んだ石)や本堂の舞台がデザインされた御朱印帳は記念品としても人気があります。
御朱印をいただく際のマナー
御朱印は単なる記念品ではなく、御本尊の分身として授けられる神聖なものです。いただく際は、まず参拝を済ませてから納経所へ向かいましょう。
また、書いていただいている間は私語を慎み、静かに待つことが大切です。書き方の指定や意見を述べるのはマナー違反となります。
清水寺で授与される御朱印の種類
清水寺では豊富な種類の御朱印が授与されており、霊場としての歴史と重要性を反映しています。境内には3ヶ所の納経所があり、それぞれ異なる御朱印を頂くことができます。授与時間は基本的に8時から閉門時刻までとなっています。
西国三十三所観音霊場の御朱印
本堂横の納経所で授与される西国三十三所の御朱印は、清水寺の代表的な御朱印です。清水寺は西国三十三所観音霊場の第16番札所として知られており、この御朱印は参拝者に最も人気があります。
本堂の御朱印には、墨書きで右側に奉拝日付、中央に「大悲閣」、左側に「清水寺」と書かれています。
朱印部分には右側に「西國十六番」、中央に梵字(キリーク)の御宝印、左側に「清水寺納経印」が押されています。「大悲閣」は観音様の仏像を安置する建物という意味で、読み方は「だいひかく」です。
また御詠歌の御朱印も同じく西国三十三所に関連するもので、本堂横の納経所で授与されています。特に西国三十三所巡礼を行っている方にとっては貴重な一枚となるでしょう。
初穂料は300円で、混雑時には15分程度待つこともありますが、窓口が複数あるため比較的スムーズに授与されます。
本堂の御朱印は「何も指定せずに御朱印をお願いします」と言うと書いてもらえる基本の御朱印です。書き置きの御朱印も用意されているので、御朱印帳を持っていない方も安心です。
洛陽三十三所観音巡礼の御朱印
洛陽三十三所観音霊場の御朱印は、京都市内の観音菩薩を祀る33ヶ寺を巡る霊場に関連するものです。清水寺では本堂横の納経所で複数の洛陽三十三所関連の御朱印が授与されています。
善光寺堂の御朱印は洛陽三十三所観音霊場の10番札所として授与されます。御朱印には墨書きで右側に奉拝日付、中央に「大悲閣」、左側に「清水 善光寺堂」と書かれ、朱印部分には「洛陽十番」の印が押されています。
このほか、奥の院の御朱印(洛陽11番)、本堂の御朱印(洛陽12番)、朝倉堂の御朱印(洛陽13番)、泰産寺の御朱印(洛陽14番)など、複数の洛陽三十三所関連の御朱印を一ヶ所でまとめて頂くことができるのが特徴です。
洛陽三十三所観音霊場は平安時代に後白河上皇が定めたとされ、明治初期の廃仏毀釈の影響で中断しましたが、2005年に復興されました。
巡礼をされる方は、清水寺だけで5種類もの御朱印を集められるのでおすすめです。初穂料はそれぞれ300円です。
阿弥陀堂の御朱印
阿弥陀堂の納経所では、法然上人二十五霊場と洛陽六阿弥陀に関連する御朱印が授与されています。清水寺の阿弥陀堂は法然上人二十五霊場の第13番札所となっています。
阿弥陀如来の御朱印(法然上人二十五霊場)は、阿弥陀堂で授与される代表的な御朱印です。法然上人は浄土宗の開祖で、この霊場は上人ゆかりの寺院25ヶ所からなります。
また御詠歌の御朱印(法然上人二十五霊場)も同じく阿弥陀堂で授与されます。これは法然上人の教えに関連する歌が記された御朱印です。
さらに、阿弥陀如来の御朱印(洛陽六阿弥陀)も頂くことができます。これは洛陽六阿弥陀第3番として位置づけられています。洛陽六阿弥陀は京都市内にある阿弥陀如来を祀る6つの寺院を巡る霊場です。
阿弥陀堂の納経所は本堂横の納経所ほど混雑することはなく、比較的スムーズに御朱印を頂くことができます。
授与時間は8時から18時までで、初穂料はいずれも300円となっています。特に阿弥陀如来信仰や法然上人に関心のある方におすすめです。
音羽の滝・不動堂の御朱印
音羽の滝の納経所では、滝ノ堂(不動堂)の御朱印が授与されています。この御朱印は不動明王の御朱印として知られ、音羽の滝を訪れた記念に頂くことができます。
音羽の滝は清水寺の名前の由来となった霊水で、「一度として枯れたことがない」と言われる霊験あらたかな場所です。滝ノ堂には不動明王が祀られており、その御朱印には「不動明王」の文字が墨書きされています。
御朱印の授与時間は8時から17時までと、他の納経所よりもやや短めですので注意が必要です。初穂料は300円です。
音羽の滝は拝観ルート上にあるため、参拝の流れの中で自然に御朱印もいただける配置となっています。
不動明王は厄除けや悪縁切りなどの御利益があるとされているため、特にそうした願いを持つ方におすすめの御朱印です。
音羽の滝の水は「健康」「学業成就」「恋愛成就」の三つの御利益があるとされていますので、滝の水を頂いた後に御朱印を頂くと良いでしょう。
地主神社の御朱印について
かつては清水寺の境内にある地主神社の御朱印も授与されていましたが、2017年4月以降は授与されていません。地主神社は縁結びの神社として人気で、恋愛成就や良縁祈願の参拝者が多く訪れる場所です。
現在、地主神社の御朱印は頂けませんが、清水寺内の他の御朱印を集めて巡るだけでも十分に満足できる御朱印巡りが楽しめます。
特に11種類の通常御朱印に加えて、期間限定で特別な御朱印が授与されることもありますので、訪問時にチェックしてみると良いでしょう。
清水寺境内の御朱印巡りルート
清水寺では、西国三十三所や洛陽三十三所観音霊場など複数の霊場の札所となっているため、様々な種類の御朱印を集めることができます。
境内には3ヶ所の納経所があり、合計11種類の御朱印が授与されています。各納経所は拝観ルート上にあるので効率よく巡ることが可能です。
効率的な巡り方
清水寺の御朱印巡りは、拝観順路に沿って進むのが最も効率的です。まず入山して仁王門をくぐり、本堂に参拝した後に本堂横の納経所に立ち寄りましょう。
ここでは7種類の御朱印が授与されており、特に代表的な「大悲閣」の文字が入った本堂の御朱印(西国三十三所第16番)を含む多くの御朱印を一度に集めることができます。
次に阿弥陀堂へ向かい、参拝後に阿弥陀堂納経所で3種類の御朱印をいただきます。法然上人二十五霊場や洛陽六阿弥陀に関連する御朱印が人気です。
最後に音羽の滝に進み、不動明王の御朱印を受け取ります。この順で巡ることで境内の主要スポットをすべて参拝しながら、効率よく全種類の御朱印を集めることができます。
御朱印巡りの際は、以下のポイントに注意しましょう:
必ず参拝してから納経所へ向かう
混雑を避けるなら午前8時〜9時頃か、午後3時半以降がおすすめ
拝観料(大人400円)とは別に各御朱印に300円の初穂料が必要
紅葉シーズンや観光ピーク時は本堂横の納経所が特に混雑するため時間に余裕を持つ
閉門時間(通常18時、7〜8月は18時30分)の30分前までには納経所へ行くようにする
納経所の場所と営業時間
本堂横の納経所
場所:清水の舞台から見て右側の建物内
御朱印の種類:7種類(西国三十三所関連2種、洛陽三十三所観音霊場関連5種、神仏霊場巡拝の道)
授与時間:8:00〜18:00(7〜8月は18:30まで)
特徴:窓口が5ヶ所あり、比較的スムーズに対応してもらえます
阿弥陀堂納経所
場所:阿弥陀堂の右側部分
御朱印の種類:3種類(法然上人二十五霊場関連2種、洛陽六阿弥陀関連1種)
授与時間:8:00〜18:00(7〜8月は18:30まで)
特徴:本堂横より比較的空いていることが多い
音羽の滝納経所
場所:音羽の滝の近く、不動堂の右側
御朱印の種類:1種類(不動明王)
授与時間:8:00〜17:00
特徴:他の納経所より早く閉まるので注意
清水寺の限定御朱印
清水寺では通常の御朱印に加えて、特定の期間やイベント時のみ授与される限定御朱印も人気を集めています。これらの希少な御朱印は、特別な思い出として多くの参拝者に喜ばれています。
季節限定の御朱印
季節限定の御朱印は、清水寺の自然の美しさと仏教行事を結びつけた特別なものです。春には桜、秋には紅葉をモチーフにした限定デザインが登場することがあります。
特に「月参り巡礼」の御朱印は西国三十三所草創1300年記念事業の一環として授与された貴重なものです。
この月参り巡礼の御朱印には、通常の御朱印に加えて右下に特別な朱印が追加されています。西国札所を月ごとに巡る特別な行事に参加した証として、参加者だけに授与される御朱印です。2017年7月18日に行われた際の御朱印は、特に格式高い仕上がりとなっていました。
御朱印の初穂料は通常と同じく300円ですが、季節限定のものは混雑することが予想されるため、時間に余裕を持って参拝するのがおすすめです。限定御朱印の情報は事前に清水寺の公式ウェブサイトで確認するか、現地でお尋ねください。
季節限定の御朱印は、その日だけの特別な縁として大切にされています。一つとして同じものはなく、その日に授かった御朱印はあなたが出会うべくして出会った特別なものと考えられています。
特別拝観時の御朱印
清水寺では春夏秋の年3回、夜間ライトアップ(夜間特別拝観)が開催されます。この特別拝観時には本堂横の納経所のみが開かれており、通常では体験できない夜の清水寺で直書きの御朱印をいただける貴重な機会となっています。
特筆すべきは、多くの寺院ではライトアップ時に直書きの御朱印を授与していないところが多い中、清水寺では夜間でも丁寧に直書きで対応してくれる点です。
夜のライトアップ時でも御朱印を求める列ができており、訪問者の体験によると10分程度の待ち時間があったとのことです。
また、清水寺の塔頭寺院である成就院(じょうじゅいん)は通常非公開ですが、毎年春(4〜5月)と秋(11〜12月)に特別公開されます。
この特別公開期間中のみ、成就院の御朱印が授与されます。こちらは書き置きのみとなりますが、美しい庭園と共に貴重な御朱印を手に入れることができる特別な機会です。
成就院の特別公開時の御朱印も初穂料は300円です。通常は見ることができない庭園の美しさと合わせて、特別な体験として人気を集めています。
特別拝観の日程は年によって異なるため、清水寺の公式サイトや現地の掲示で最新情報をご確認ください。
手書きの御朱印は、一文字一文字に込められた思いが特別な意味を持ちます。特別拝観時の御朱印は、通常とは異なる雰囲気の中でいただける貴重なものですので、ぜひ御朱印帳を持参して訪れてみてください。
オリジナル御朱印帳
清水寺では独自のオリジナル御朱印帳も授与されています。紺とピンクの2色があり、表紙には清水寺の象徴である「舞台」をデザインした金色の箔押しが施されています。裏面には清水寺の寺紋が入った格式高いデザインです。
このオリジナル御朱印帳は本堂横の納経所でのみ取り扱われており、清水寺らしい品のある表紙が特徴です。
御朱印帳の値段は2,000円程度で、清水寺の思い出として、また御朱印集めの始まりとして人気があります。
清水寺オリジナルの御朱印帳
清水寺では魅力的なオリジナル御朱印帳が複数種類販売されています。これらの御朱印帳は本堂裏にある納経所のみで購入できるため、御朱印と一緒に入手するのが効率的です。
公式御朱印帳の種類と特徴
清水寺の公式御朱印帳は現在3種類あり、それぞれ特徴的なデザインが施されています:
清水の舞台デザイン:エンジと紺の2色があり、表紙には清水の舞台が描かれています。裏表紙には清水寺の寺紋と「音羽山清水寺」の文字が金襴であしらわれています。
値段:1,650円
サイズ:縦18cm×横12cm×厚さ1.5cm
材質:表紙は布製
様式:蛇腹式
錦雲渓デザイン:紅葉した木々に包まれた本堂と舞台、青空をいちょう色でデザインした御朱印帳です。
値段:1,650円
サイズ:縦18cm×横12cm×厚さ1.5cm
法輪デザイン:古代インドの武器を起源とする「法輪」をモチーフにしたデザイン。金色の唐草模様で描かれ、高級感のある御朱印帳です。唐草模様は吉祥を示す模様とされています。
値段:1,650円
サイズ:縦18cm×横12cm×厚さ1.5cm
特別な御朱印帳
一般的な御朱印帳に加え、特別なコレクション価値の高い御朱印帳も販売されています:
写刺織御朱印帳:丹後地方で生まれた写真織りとデジタル加工を施した「写刺織」技法で作られた御朱印帳。高級感があり、精緻な仕上がりが特徴です。
値段:8,500円
サイズ:縦18cm×横12cm×厚さ1.6cm
几帳生地使用御朱印帳:清水寺境内の諸堂の柱間に吊るされていた几帳(きちょう)を使用した御朱印帳。生地や柄が一点一点異なる特別なコレクションアイテムです。
値段:3,300円
サイズ:縦18cm×横12cm×厚さ1.6cm
特徴:清水寺の住職 森 清範 貫主による題字入り
西国三十三箇所専用御朱印帳:日本最古の巡礼「西国三十三箇所巡り」の専用御朱印帳。清水寺は西国三十三箇所巡りの第16番霊所に指定されています。
値段:1,000円
御朱印帳の選び方
御朱印帳には蛇腹式と和綴じの2種類があります:
蛇腹式:山折谷折りで閉じられた形式で、和紙をひと続きにして御朱印をいただくため、広げると御朱印が順に並びます。次に書いてもらう場所を探しやすいため、初めての方におすすめです。
和綴じ式:本のように紐で綴じてあり、紐をほどけば御朱印の順番を入れ替えられます。こだわりがある方に適しています。
サイズは文庫本サイズやB6サイズが一般的で使いやすいため、最初はこれらのサイズから選ぶとよいでしょう。
清水寺周辺の御朱印スポット
清水寺での御朱印巡りは、本堂だけで終わらせるのはもったいない。清水寺周辺には魅力的な御朱印スポットが点在し、一日かけて巡ることで京都の歴史と文化をより深く体験できます。
地主神社
地主神社は清水寺と同じく世界遺産に登録されており、清水寺の守護神として古くから崇められています。清水寺の境内から約2分の場所に位置し、縁結びの神社として特に女性に人気があります。
境内には恋占いの石や地主桜など見どころが多く、参拝客で賑わっています。残念ながら現在は御朱印の授与を行っていませんが、以前は「地主神社」の文字と神紋が入った美しい御朱印が授与されていました。
地主神社では御朱印こそありませんが、縁結びのお守りや絵馬などの授与品が充実しています。特に恋占いの石は、目を閉じて片方の石から反対側の石まで歩いて辿り着けると、恋愛が成就すると言われており、参拝者の間で人気の体験スポットです。
授与所の時間は9:00から17:00までで、混雑時には整理券が配布されることもあります。清水寺参拝の際には、ぜひ足を延ばして訪れたい神社です。
八坂の塔(法観寺)
八坂の塔として親しまれている法観寺は、清水寺から徒歩約8分の場所に位置しています。東山のシンボルとして知られる五重塔が特徴的で、京都の風景を代表する建造物の一つです。
法観寺の御朱印は御本尊の薬師如来と「八坂の塔 法観寺」の文字が墨書きされた伝統的なデザインで、漆黒の墨と朱印のコントラストが美しいです。
御朱印料は300円で、塔内の受付で授与されています。手書きの御朱印が基本ですが、住職不在時には書き置きの場合もあります。
特筆すべきは塔の内部が拝観できることで、二層部分まで上ることができます。内部からの眺めは格別で、御朱印巡りの合間に一息つける絶好のスポットです。
拝観時間は10:00から16:00まで(最終受付15:30)で、拝観料は大人400円です。清水寺と八坂神社を結ぶ通りに位置しているので、御朱印巡りのルートに組み込みやすい場所です。
八坂庚申堂
八坂庚申堂は清水寺から徒歩約10分、法観寺のすぐ近くに位置しています。日本三庚申の一つに数えられる古刹で、近年ではカラフルな「くくり猿」が吊るされた境内がSNS映えスポットとして人気を集めています。
御朱印は「八坂庚申堂」の文字と共に、「見ざる・聞かざる・言わざる」の三猿の印が押される特徴的なデザインです。
三猿の印は庚申信仰の象徴であり、他では見られない貴重な御朱印です。御朱印料は300円で、授与時間は9:00から17:00までです。
境内には色とりどりのくくり猿が奉納されており、季節や願い事によって色が異なります。くくり猿とは、欲望のままに行動する猿の手足を縛ることで自分の心を戒めるために作られたお守りで、一つの欲を我慢して奉納することで願いが叶うと言われています。
特に庚申の日(干支が申の日)には多くの参拝者が訪れ、御朱印を求める人も増えるため、庚申の日を避けて訪問するか、早めの時間に訪れることをおすすめします。手書きの御朱印のみで書き置きはないため、時間に余裕を持って訪問しましょう。
御朱印巡りの際の注意点とマナー
参拝順序と時間
清水寺での御朱印巡りは、まず参拝を済ませてから御朱印をいただくのが正しいマナーです。御朱印の授与時間は8:00~18:00で、境内への入場時間は6:00~18:00です。
紅葉や桜の季節は非常に混雑するため、午前中の早い時間か夕方に訪れるとスムーズに御朱印をいただけます。納経所は拝観ルート上に配置されているので、順路に沿って巡るのが効率的です。
御朱印の種類と金額
清水寺では通常10種類の御朱印が常時授与されています。それぞれの御朱印の初穂料は300円です。季節や特別行事の際には限定御朱印も登場するので、事前に公式サイトで確認しておくと良いでしょう。御朱印をまとめて複数種類いただく場合も、一つずつ初穂料を納めるのがマナーです。
御朱印帳の持ち方
御朱印帳は左手で持ち、右手で納経所の方に渡すのが基本です。両手で丁寧に渡し、受け取る際も同様に両手で受け取りましょう。
初めて御朱印巡りをする方は、蛇腹式の御朱印帳が次の書き込み場所を探しやすく便利です。清水寺ではオリジナルの御朱印帳も販売されているので、記念に購入するのもおすすめです。
納経所での振る舞い
納経所では静かに並び、順番を守りましょう。御朱印を書いていただいている間はスマートフォンの操作や私語は控え、写真撮影も禁止です。
納経所では「御朱印をお願いします」と丁寧に依頼し、いただいた後は「ありがとうございました」と感謝の言葉を述べるのがマナーです。
御朱印の授与場所
清水寺の境内には、本堂横の納経所、阿弥陀堂、音羽の滝という3ヶ所の納経所があります。本堂横の納経所では7種類、阿弥陀堂では3種類、音羽の滝では不動明王の御朱印1種類がいただけます。すべての御朱印を集めたい場合は、3ヶ所すべてを訪れる必要があります。
手書きと書き置きについて
清水寺では基本的に御朱印は手書きで授与されますが、大変混雑する時期には書き置きの御朱印が用意されることもあります。
書き置きでも同じ御朱印を授かれることに変わりはなく、同様にありがたくいただきましょう。特別な日やイベント時には直書きの特別御朱印が授与されることもあるので、機会があれば体験してみるのも良いでしょう。
まとめ:清水寺での御朱印巡りを楽しもう
清水寺での御朱印巡りは 京都旅行の特別な思い出になりますよ。全11種類の御朱印を3ヶ所の納経所で集めることで 清水寺の歴史と魅力をより深く感じることができます。
本堂横 阿弥陀堂 音羽の滝と巡りながら それぞれの場所で異なる御朱印をいただく体験は とても充実したものになるでしょう。季節限定の御朱印やオリジナル御朱印帳も見逃せません。
参拝マナーを守りながら 早朝や夕方の比較的空いている時間帯を選んで訪れると より良い体験ができますよ。清水寺の御朱印巡りを通して 京都の歴史と文化に触れる素敵な旅になりますように。
質問:FAQs
清水寺の御朱印は何種類ありますか?
清水寺では全11種類の御朱印が用意されています。本堂横の納経所では7種類、阿弥陀堂では3種類、音羽の滝では1種類の御朱印を受け取ることができます。
これらには西国三十三所や洛陽三十三所の御朱印も含まれており、季節限定の特別な御朱印も時期によって授与されます。
清水寺の御朱印の初穂料はいくらですか?
清水寺の御朱印の初穂料は1体につき300円です。これは参拝の証として納めるもので、拝観料とは別に必要となります。特別な限定御朱印も同じ初穂料で授与されることが一般的です。
清水寺の御朱印はどこでもらえますか?
清水寺の御朱印は境内の3ヶ所で受け取れます。本堂横の納経所(7種類)、阿弥陀堂納経所(3種類)、音羽の滝納経所(1種類)があります。
それぞれ異なる御朱印を授与しているため、すべての御朱印を集めたい場合は3ヶ所すべてを訪れる必要があります。
清水寺の御朱印の受付時間は?
清水寺の御朱印授与時間は朝8時から夕方18時(季節により18時30分)までです。境内への入場時間は6:00~18:00となっています。特に紅葉や桜の季節は混雑するため、午前中の早い時間か夕方に訪れることをおすすめします。
清水寺のオリジナル御朱印帳はありますか?
はい、清水寺では独自のオリジナル御朱印帳が販売されています。本堂裏の納経所で購入でき、現在3種類のデザインがあります。それぞれ清水寺の特徴を反映したデザインで、御朱印巡りの記念として人気があります。
清水寺で御朱印をもらう際のマナーは?
清水寺で御朱印をいただく際は、まず参拝を済ませてから納経所に向かいましょう。御朱印帳は両手で丁寧に渡し、受け取る際も同様に両手で受け取ります。
納経所では静かに並び、順番を守り、丁寧に依頼し、受け取った後は感謝の言葉を述べることがマナーです。
清水寺の季節限定御朱印はいつもらえますか?
清水寺の季節限定御朱印は、春の桜シーズンや秋の紅葉シーズンなど特定の期間に授与されます。また、「月参り巡礼」の御朱印や特別拝観時の夜間ライトアップ期間中の御朱印など、特別なイベント時にのみ授与される貴重なものもあります。公式サイトや現地で最新情報を確認しましょう。
清水寺の御朱印巡りの効率的なルートは?
清水寺での効率的な御朱印巡りは、仁王門から入り本堂に参拝した後、本堂横の納経所で7種類の御朱印を集め、次に阿弥陀堂で3種類、最後に音羽の滝で不動明王の御朱印を受け取るルートがおすすめです。拝観順路に沿って進むことで、スムーズに全ての御朱印を集めることができます。
清水寺は混雑しますか?
はい、清水寺は年間500万人以上が訪れる京都の人気観光スポットであり、特に桜や紅葉のシーズンは非常に混雑します。
御朱印を授与してもらう際も行列ができることがあります。混雑を避けるには、平日の早朝や夕方に訪れるのがおすすめです。
清水寺周辺で他に御朱印がもらえる場所はありますか?
清水寺周辺には、高台寺、八坂神社、知恩院など多くの寺社があり、それぞれ独自の御朱印を授与しています。
これらを組み合わせて東山エリアの御朱印巡りを楽しむことができます。時間に余裕をもって訪れれば、一日で複数の寺社を巡ることも可能です。